今回読んだ本は『仕事の「整理ができる人」と「できない人」の習慣』です。
この本は、モノ、思考、心、人間関係を整理するコツを教えてくれます。
今回はその中でも、モノやデータの整理にフォーカスして紹介します。
その他も知りたいという人は、ぜひ本書を読んでください。
上司:ちーぱぱさん、あのデータ見せて。
ちーぱぱ:はい。えーっとどこにやったっけ。モタモタ…
上司:ちーぱぱさん、あのデータ見せて。
ちーぱぱ:はい、こちらです。
後者の方が圧倒的にスマートでかっこいいですよね。
ビジネスパーソンは、年間150時間も探し物をしています。
これは全く意味のないムダな時間です。
できればこのムダな時間を減らして、もっと大切なことに充てたい。
そこで今回は、モノを見つけやすくするコツを3つ紹介します。
【読書にはKindleがオススメ。理由はこちら】
サラリーマンがKindle Paperwhiteを買うべき3つの理由
1年間使わなかったものは手放す
モノを見つけやすくするには、上手に片付けることがポイントです。
そこでまずは「片付け」とは何かを定義しておきましょう。
片付けとは、「整理」→「収納」→「維持」のサイクルを回すことです。
整理:必要・不要を分けて、不要なモノは手放す
収納:必要なものをすぐに取り出せるようにスタンバイする
維持:使ったモノはもとに戻す、モノが増えたら減らす
特に重要なのが、「整理」と「収納」の順番です。
モノを減らさないまま、いくら上手に収納しても、
いずれモノが増えていき崩壊します。
むしろ、きれいに収納できてしまうことで、
「もっと増やせる」とモノを増やすことに拍車をかけてしまう可能性すらあります。
なので、「整理から始める」ことが重要です。
そして整理するときに有効な考え方が、
「1年間使わなかったモノで、使う日程が現時点で決まっていないモノは手放す」です。
アメリカのナレムコ(国際記録管理協会:National Records Management Council)の統計によると、
作成や収集された文書のうち、半年後も使用される文書が10%、
1年後には1%の文書しか利用されないとのことです。
つまり、1年間使われなかったモノは、その後も99%使われないということです。
なので私は、1年間使わなかったデータは削除しています。
そうすることで必要なデータが見つかりやすくなりますし、
その後の整頓(収納)もしやすくなります。
今のところデータがなくて困ったこともありません。
1%の確率で困るのを恐れるより、
毎日必要なデータに速くたどり着けることの方が良いと思いませんか?
資料はすべてデータ化する
資料はすべてデータ化しましょう。
紙の資料もスキャンすることでデータ化できます。
データ化することのメリットは2つです。
- 探しやすくなる
- PCがあればどこでも確認できる
1つ目は「探しやすくなる」ことです。
紙でとっておくと、必要な情報を探し出すのに時間がかかります。
データ化すれば、PC上で検索機能を使うことで探しやすくなります。
2つ目は「PCがあればどこでも確認できる」ことです。
紙の場合、常に持ち歩かない限り、基本的には会社のデスクにしまうことになるかと思います。
ただそうすると、外出先で見たくなったときに見れません。
データ化しておけば、PCさえあればどこでも確認できます。
私はもう紙の資料を持っていません。
デスクの引き出しは空っぽです。
あなたもぜひ紙資料のデータ化をお試しください。
フォルダのルールを決める
データを整頓(収納)するときにおすすめなのが、
「フォルダのルールを決める」ことです。
本書の中では「配置の一貫性」として、
どこでも[職場でも自宅(在宅)でも]モノの配置を同じにすることで、
置くとき、探すときの脳のエネルギー消費を減らせると紹介されています。
これはPC内のフォルダ構成でも使えます。
フォルダ構成をルール化しておくことで、
新たなデータをどこに格納すればいいのかが明確になり、
以前作成したデータがどこにあるのかもわかりやすくなります。
それにより脳のエネルギーを節約することができます。
例えば私の場合は次のようなルールにしています。
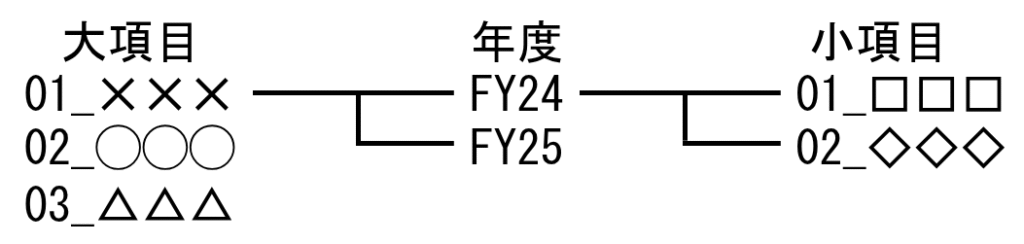
あなたもフォルダのルールを決めて、脳のエネルギーを節約しませんか?
まとめ
今回は『探す時間はムダ!モノを見つけやすくするコツ3選』を紹介させていただきました。
あなたの探す時間削減の一助になれば嬉しいです。
- こんなときはどうするの?
- こういう考え方もあるよね?
こういったコメント大歓迎です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

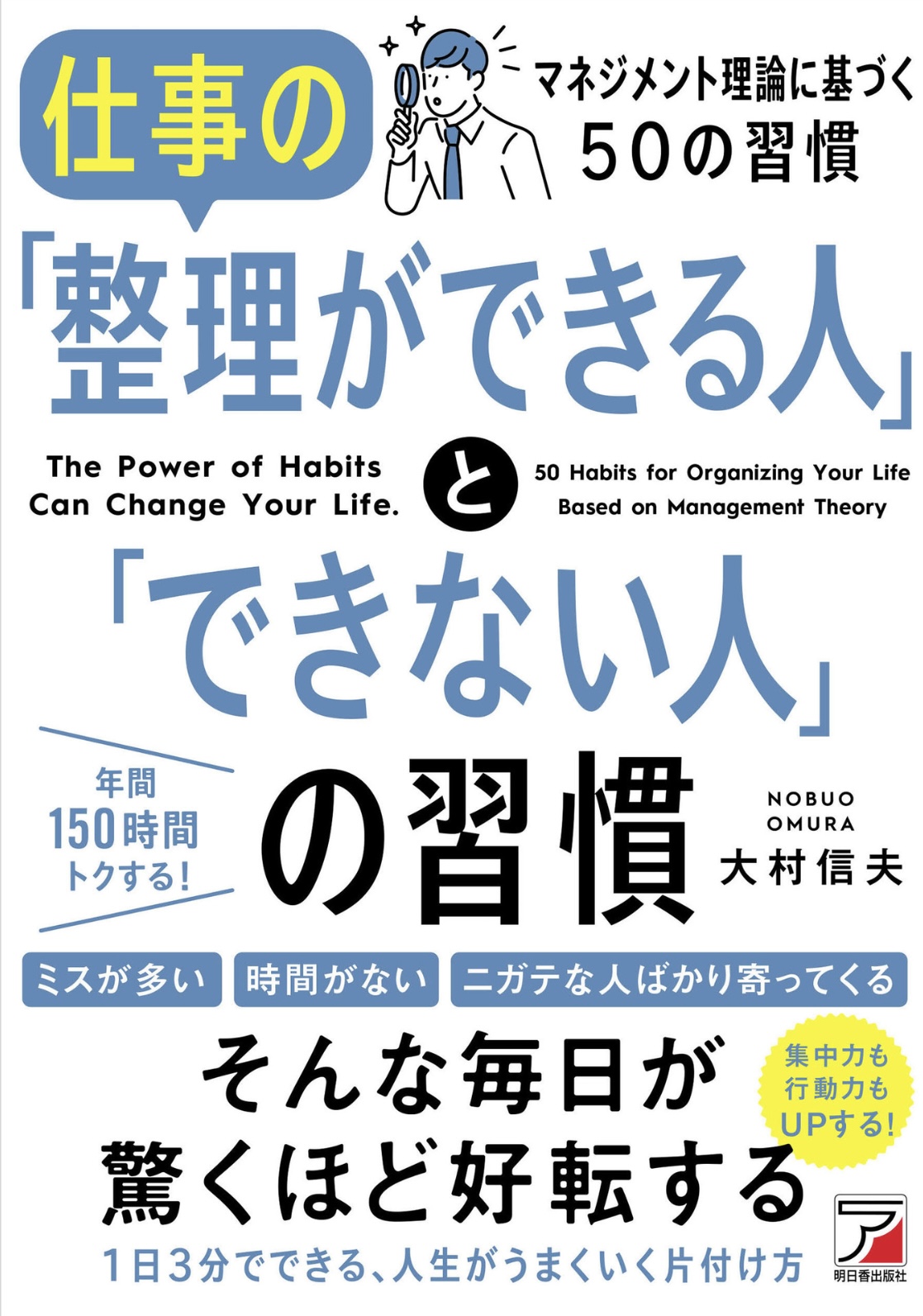
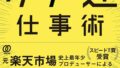
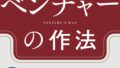
コメント