今回読んだ本は「良い戦略、悪い戦略」です。
この本は、良い戦略を立てる手助けをしてくれます。
「頑張ってるのになかなか成果に結びつかない…」
こんな悩みを持っていませんか?
それはモノゴトを戦略的に考えられていないからかもしれません。
モノゴトを戦略的に考えることで、効率良く成果を出していくことができるようになります。
「戦略とは何か」「戦略的に考えるとはどういうことか」については、
過去に記事を書いているので、ぜひこちら(頑張っているのに結果が出ない理由はこれかも?戦略的思考のススメ)を読んでみてください。
今回はさらに深堀って、
戦略を立てるための、戦略的思考の3ステップを紹介します。
【読書にはKindleがオススメ。理由はこちら】
サラリーマンがKindle Paperwhiteを買うべき3つの理由
診断する
戦略的思考の第一歩は、「今何が起きているのか」をはっきりさせることです。
事実を客観的に観察して問題点を把握します。
これをしないと現実的な戦略を立てることはできません。
これをやらずに立てた戦略は、ただの推測です。
逆に、状況を適切に診断できれば、
複雑な状況が整理され、よりシンプルな形で問題点が提示されます。
そうすると、どこに注意を払うべきかがとてもわかりやすくなります。
- どこは問題なく機能していて
- どこに問題が起きているのか
- それはどんな問題か
- どの問題は解決可能で
- どの問題は解決不可能か
こういったことを明確にすることが診断です。
診断を丁寧に実施することで、どこにアプローチすることが効果的かが浮かび上がってきます。
なにか問題にぶつかったときは、まず事実を確認し、状況を丁寧に把握しましょう。
基本方針を決める
診断結果で明確になった問題に対し、
- どれにアプローチするか
- どれにはアプローチしないか
を決めます。
ここでは大きな方向性だけを指し示し、具体的に何をすべきかは決めません。
アプローチする場所としない場所を明確にすることが、基本方針を決めるということです。
これにより、リソースを集中させる場所を明確にします。
選択肢が複数ある場合はリスト化し、優先順位を決め、上のものを選択します。
しっかりした基本方針を決めることで、その後の行動を次々決めることができ、
あちこち目がいかず目標達成に集中することができます。
注意点は、特にやらないことを決めるには様々な抵抗を伴うため、
そこには「ノー」と言う勇気とリーダーシップが必要になることです。
これについては、最初の診断を丁寧に実施し選択の根拠を明確にすることが、
基本方針の芯を太く強いものにしてくれます。
行動を決める
基本方針が決まったら、最後にその方針に沿った具体的な行動を決めます。
行動を決める上で大事なポイントは1つ。
それは、「近い目標」を定めることです。
近い目標とは、手の届く距離にあって、十分に実現可能な目標のことです。
高い目標を設定することは問題ないですが、達成不可能であってはダメです。
そんなことをしたら、せっかく診断で問題を見極め、
基本方針でリソースを集中させる場所を選んだのに、
最後の最後にリソースを無駄遣いする行動を選択することになってしまいます。
必ず手の届く距離にある「近い目標」を設定しましょう。
まとめ
今回は『戦略はこう立てる。戦略的思考の3ステップ』を紹介させていただきました。
あなたの努力が成果に結びつきやすくするための一助になれば嬉しいです。
- こんなときはどうするの?
- こういう考え方もあるよね?
こういったコメント大歓迎です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

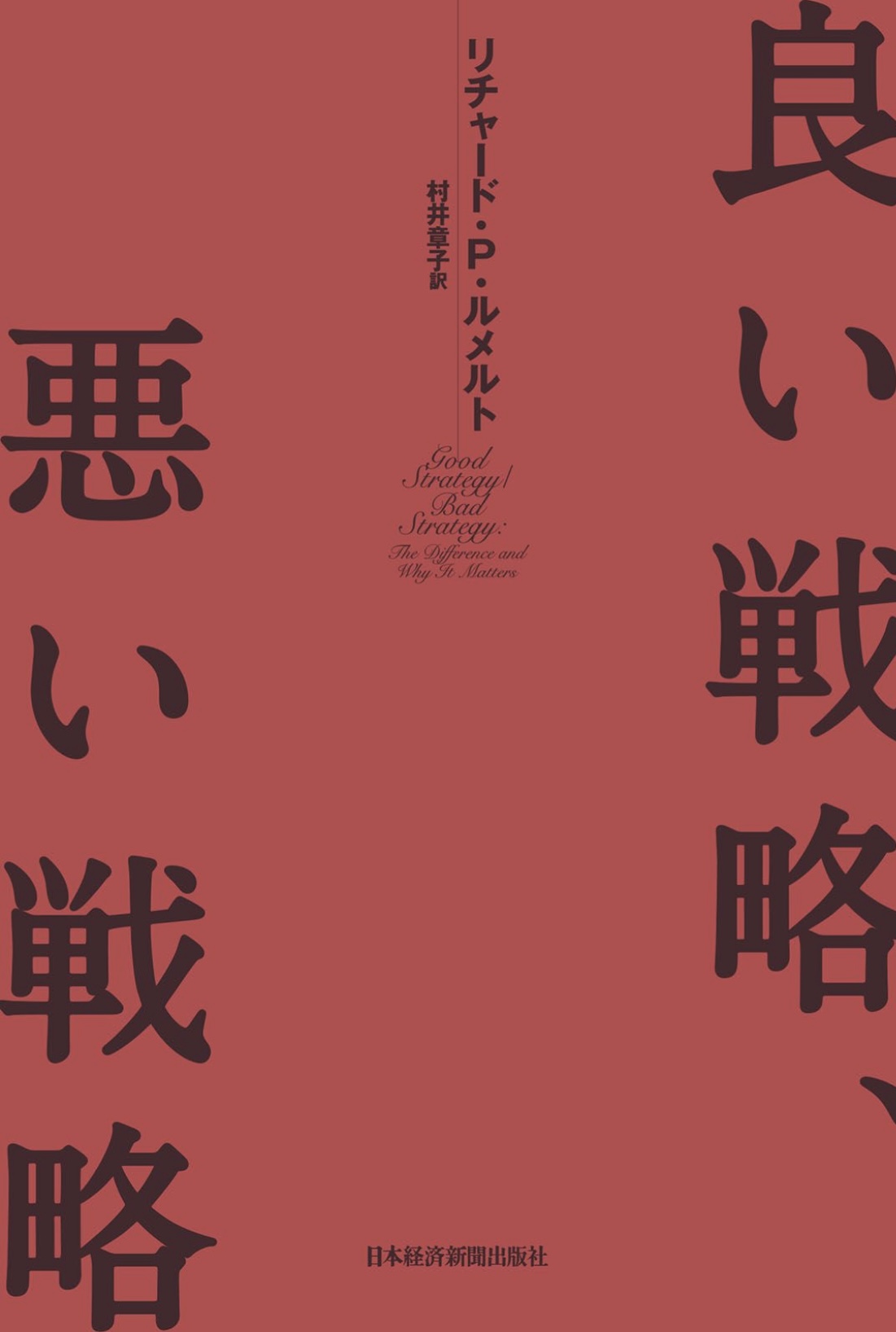


コメント